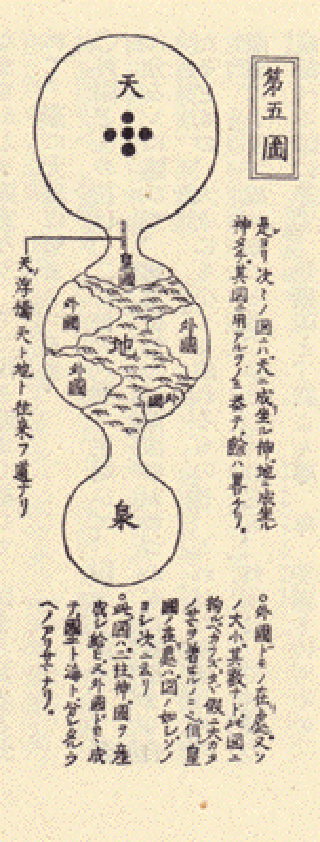
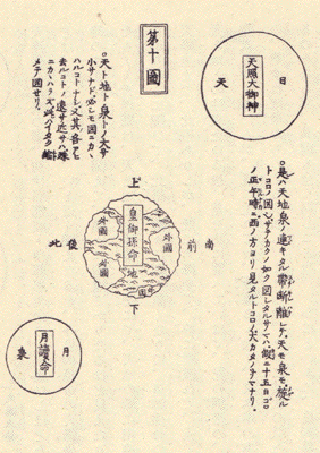
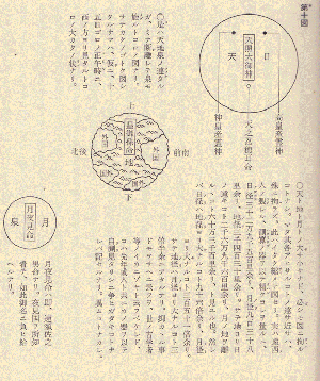
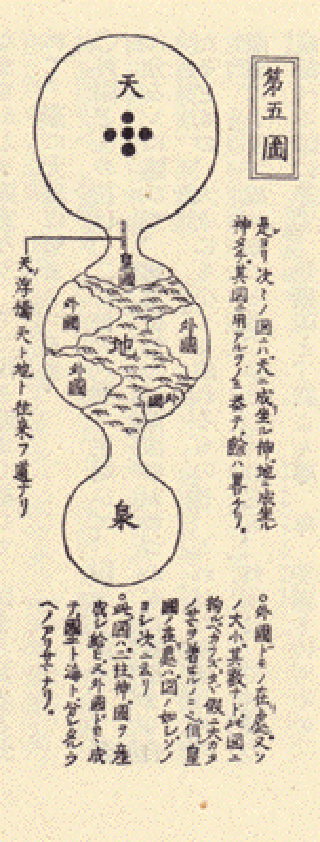
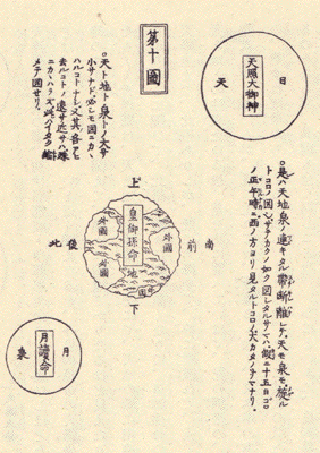
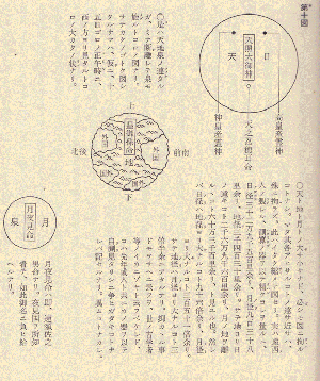
要するに太陽、地球、月はもともとひとつのカオスから次第に分かれて形成されたという説が西欧の書物にあり、このことは古事記の最初に語られる国生みの中で語られている物語のことである、と平田が主張しているのである。
この辺までは、ふーん、まあ、そういうこじつけもありかな、と我慢できるのであるが、さらに平田の話は、延々とつづくのである。太陽は天照大神がおられるところ、地が皇国(我が国)、月は黄泉の国という死者の行くところであるという。
とくに最大の問題点であるのは、平田篤胤の語る死後の世界というものである。第一にそれまでの伝統的な精神とは質的にまったく違ったものであることをまず、上げなければならない。さらに、第二に伝統的精神と違っているということだけでなく、だれもどの文献でもそれまで一言も語られたことのない、怪しげな見解であるということを言わざるを得ないのである。
次に引用したくだりが、篤胤の語る死後の世界なるものである。"霊の真柱”という篤胤の代表的な著作に出てくるくだりである。そして、この死後の世界こそ、靖国の死して後、靖国の桜となって会おう”、というスローガンの原点となった、きわめて歴史的には重要な文言なのである。
〈略解〉 おおよそ志を同じくする仲間、おなじ運動に身を投じた人々は、死後もその魂が同じところに集まり、お互いに助け合うのであって、このことは日本や中国の様々の書物に記述され伝えられてきた事実である云々
もともと古事記には、日本の国を生み出した女性の神・いざなみは、黄泉の国という暗く恐ろしく、同時に非常に穢らしい世界に行ったと書かれている。黄泉の国とは死者の行く世界なのである。ところが、篤胤はこころざしが素晴らしく、みごとな死に方をした人々は、黄泉の国に行くのでなく、冥界という、冥界からはこの世がみえるが、この世からは見ることができないところにあって、この世の良き場所にたがいに集い有って、末永く住むことが出来るということを言い出した。
したがって、第一の問題点である、古事記・日本書紀に著されている伝統の死後の世界と平田の言う死後の世界とはとはまったくかけ離れているということがはっきりしていることがお分かりであると思うのである。平田が自身の永遠の師匠と呼ぶ古事記伝の著者である本居宣長の考えと、まったく相容れないのである。すなわち、本居宣長は、古事記の伝統の考えに則り、死者の行く黄泉の国とは、穢れた近寄りがたい世界であって、決して黄泉の国に行った人を後追いするようなことがあってはならないと考えていた。そして、死後の世界というものを宗教家でもない篤胤が、分を超えてしつこく詮索することに対し、宣長の弟子たちは快く思っていなかったことはよく知られているのである。
第一の問題点からみて、篤胤がもし、自分は古来からの変わらぬ古来伝統の神道を世に知らしめているのである、と主張するのであれば、この不思議な、平田しか語っていない摩訶不思議な独特の生死観は、古来の死後の世界観ではまったくないわけで、自分で自分を否定する、あきらかな自語相違であることは明白であろう。
さらに、第二の観点からみて、この平田の摩訶不思議な死後の世界というのは、いったい何なのかということを考えるには、平田という人物をもう少し知ってみる必要があるのである。
平田は、結婚して10年目、この”霊の真柱”という著作を執筆している最中に、最愛の女房が病死しているのである。この女房は綾瀬という名の女性で、平田が久保田正吉として、とある旗本のところで丁稚奉公していたとき、同じ奉公先で知り合った、武家の養女として引き取られた、とある武家の後妻の連れ子であった。この連れ子とはいえ、れっきとした旗本の娘である。当時正吉と呼ばれていた平田は、田舎から素浪人として故郷を追われて江戸へ転がり込んできた卑しい使用人の身分である。とても一緒になれるような相手ではなかったことは容易に想像がつくのである。ところが、一角の人物として拾い上げて下さった備中岡山藩譜代大名にして藩主の勝政公と、養父となった平田藤兵衛篤穏のたいへんな骨折りで、なんと二人は夫婦になることができたのであった。
現代でいうと、”純真純情な同級生夫婦”のごとき人生だったのである。この女性は、すくない家禄から二人三脚で苦労し、出版活動費や書籍代、公演の旅費の工面等ひねりだしてくれていたのである。
平田の研究者の伊藤 裕氏によると、もともと漢文・漢書を読みあさって素読を日常の習慣としていた平田に、古事記伝という本居宣長の書物の存在を教えたのは、この綾瀬であると指摘されている。通常なら、論語、詩書の読み書きの先生あたりで人生を終えていたかもしれない平田に、この国学への道を示して、国学者としての道を拓いてくれたのがこの恋女房だったとすると、平田の著述人生はある意味で、この女性のために捧げられたものであるとも言える。
悲嘆にくれた篤胤が、最愛の恋女房の病死のため、一時期まったく廃人のようにぼんやりを日々を送るだけになったのであった。ところが、ある日を境として、決然として、ふたたび著述に講演に没頭まい進していゆくのである。
ただ、篤胤の様子は悲しみをのりこえて超越した境地で著作に励んだ、という印象とはどうも違うことに徹底して注目しなければならないのである。平田は亡くなった綾瀬に、ひたすら悲しみの情を切々と綴る歌や文章をたくさん残している。そして、綾瀬とひたすら会いたい、夢の中でも会いたいを思いという強い情念に強く囚われて、どうも空想と現実の境が見えなくなった精神状態での執筆活動しているような様子が十分推測されるのである。もともと平田には最初の世界観の話のように現実と空想の境目がきちんとしていない、夢であるとかお告げとかにやたらとこだわる人物像があるのだが、さらにその姿勢がエスカレートしてゆくのである。
ここに、ひとつ重大な事実を書き留めておく必要がある。篤胤という人物は身内を病気でつぎつぎと失っていった人なのである。平田家の跡取りとして、養父母ともども、皆が大事に大事に愛情を注いてきた長男・常太郎は1歳で”はしか”のため病死するのである。篤胤の必死の祈祷、医者としての治療も虚しく、亡くなっていったのである。のちに長女と次男が誕生するのであるが、長女は後世まで生きて人生を全うされているが、次男・又五郎は5歳で”水痘”で亡くなっているのである。
まことに厳しい言い方であるとは思うが、私は、平田の身に起こる身内の死という不幸とは、残念ならがある意味で当然の帰結であると思うのである。というのも、もともと神道とは古事記の生死観の通り、死というものを忌むべきもの、生きている世界にすむ人ならば、悪霊とりつかれて不幸に見舞われないようひたすら遠ざけ、封じ込めるものという認識なのである。平田がひたすらこだわった神道とは、もともと病、不幸と、真っ向から向き合おうとするもではない。平田が神道に拘ればこだわるほど、ますます不幸のループに落ち込んでゆくというものなのである。
そして、神道と仏教、儒教に関わる実に膨大なことについて、事細かに著述して、分かりやすく庶民にも講演してきている平田なのであるが、平田の主張には実は、あきらかに一つ、意図的に事実とは異なるおかしなことを言っている箇所があることを、ここではきちんと指摘しておくことにする.
それは仏教伝来に関わる重大な事実に関することである。
まず、篤胤の講演筆記にでてくる仏教伝来の箇所を抜き出してみると、以下のようになる。
甲賀寺ノ盧舎那仏建立(甲賀宮=紫香楽宮に大仏造営が一時期計画されていたことをさす)ノミギリハ、(補足:聖武天皇が)大御手ズカラ其縄ヲ御引キアソバシ、孝謙天皇ヘ御位ヲ御譲リアソバシテノチ、勝蔓トイフ法師名ナンドヲ御ツケアソバシ、御位ニアラセラレタル間ノ御行状、スベテノ御ワザモ大カタハ佛ワザノヨウデアリ、マタ此御代ニ始メテ痘瘡(モガサ)ノ病ガ御国ニ傳ワリ、又御代御代ニ、未ダキキモ及バヌ程ノ疫病ナドハヤッテ、更ニ佛法ヲ御信ジアソバシタル験ハナク、悪キコトオオカッタノジャ。(平田篤胤全集:平田篤胤全集刊行会.2001年、名著出版。p127、俗神道大意一).
という記載があるのであるが、痘瘡がはじめて我が国に伝播したのが聖武天皇の代であると述べている。そして、聖武天皇は大仏の造営をはじめとして仏法を深く信じた”佛ワザ”の天皇であったため、痘瘡をはじめとする、得体のしれない疫病が流行して、仏法を信じているのにいっこうに良いことがなく、悪いことが多かった、と主張するのである。
この主張は、日蓮大聖人が四条金吾殿(別名告誡書、大石寺版p1175~1177)に与えられた御書の御金言に出てくる仏法伝来にまつわる深い物語とまったく異なっていることを、ここではっきりと指摘しておきたい。
まず平田は、痘瘡という重大な病に対する認識がまったく間違っているのである。痘瘡が我が国に伝播したのは六世紀の終わり、580年代である。そして、敏達天皇、用明天皇を始めとする上下万民が痘瘡にかかり、亡くなっていった、まことに大変な事態を引き越したことが日本書紀にはっきりと記されているのである。したがって、平田が取り上げているのは、平城京で流行した735年から738年のその後の大流行のことである。日本書紀を熟読していたはずの平田であろうから、この流行の前に痘瘡が流行していたということを知らないはずがないのである。すなわち、第一回目の流行のときには、大変な事態が起き、この流行を契機に神道派の巨魁・物部氏が滅亡するという大事件が起きているため、取り上げるのが非常に都合が悪いということなのである。つまり、俗神道大意中の平田の記述は、あきらかに初回の痘瘡の大流行のことを伏せて、無視していることになる。つまり、認識が間違っているというよりは、意図的に都合のよいところだけを取り上げて、上記の講演をやっていたということなのである。
この初回の痘瘡の大流行のため、父である用明天皇、叔父である敏達天皇を亡くされた聖徳太子が、ひとりはっきりと三宝に帰すことを決意され、物部守屋等を斥けて、とりあえず第一回目の痘瘡流行の克服を見たということは歴史的事実である。日蓮大聖人は、この事実を正確に把握され、さまざまの御書に御金言を残されているのである。とくに、この四条金吾殿御返事にいちばんまとまって仏法伝来の歴史事実が記されているので、少々長いが以下にこの四条金吾殿ご返事の中の、仏法伝来と天皇、氏族たちの生きざまがいきいきと記されている部分を抜粋させていただいた。
『この国に仏法わたり由来をたづぬれば、天神七代・地神五代すぎて人王の代となりて、第一神武天皇乃至第三十第欽明天皇と申せし王をはしき。位につかせ給いて三十二年治め給いしに、第十三年壬申十月十三日辛酉に、この国より西に百済国と申す国あり。日本国の大王の御知行の国なり。その国の大王聖明王と申せし国王あり。貢を日本国にまいらせしついでに、金銅の釈迦仏並びに一切経・法師・尼等をわたりたししかば、天皇大いに喜びて群臣に仰せて云はく、西蕃の仏をあがめ奉るべしやいなや、蘇我の大臣いなめの宿禰と申せし人の云はく、西蕃の諸国みな此を礼す、とよあきやまとあに独り背かんやと申す。
物部のおおむらじをこし・中臣かまこ等奏して曰く、「我が国家天下に君たる人は、つねに天地・しゃそく・百八十神を春夏秋冬にさいはい(祭拝)するを事とす。しかるをいまさらあらためて西蕃の神を拝せば、をそらくは我が国の神いかりをなさん」云云。爾の時に天皇わかちがたくして勅宣す。此の事を只試みに蘇我の大臣につけて一人にあがめさすべし。他人用ひる事なかれ。蘇我の大臣うけ取て大いに悦び給ひて、この釈迦仏を我が居住のおはだ(小墾田)と申すところに入れまいらせて安置せり。
物部大連不思議なりといきどおりし程に、日本国に大疫病をこりて死せるもの大半に及ぶ。すでに国民尽きぬべかりしかば、物部大連隙を得て此の仏を失ふべきよし申せしかば勅宣なる。「早く他国の仏法を棄つべし」云云。物部大連御使ひとして仏をば取て炭をもてをこし、つち(槌)もて打ちくだき、仏殿をば火をかけてやきはらひ、僧尼をばむちをくわう。その時晴天に雲なくして大風ふき、雨ふり、内裏天火にやけあげて、大王ならびに物部大連・蘇我臣三人共に疫病あり。きるがごとく、やくがごとし。大連は終に命絶えぬ。蘇我と王とはからくして蘇生す。而れども仏法を用ゆることなくして十九年すぎぬ。
第三十一台の敏達天皇は欽明第二の太子、治十四年なり。左右の両臣は、一は物部大連が子にて、弓削守屋父のあとをついて大連に任ず。蘇我の宿禰の子は蘇我馬子と云云。この王の御代に聖徳太子生まれ給へり。用明の御子敏達のをいなり。御年二歳の二月、東に向かって無名の指を開いて南無仏と唱え給えば御舎利掌(みて)にあり。是日本国の釈迦念仏の始めなり。太子八歳になりしに八歳の太子云はく「西国の成人釈迦牟尼仏の遺像、末世に之を尊めば則ち禍ひを消し福を蒙る。之を蔑(あなず)れば則ち災いを招き寿を縮む」等云云。
大連物部弓削宿禰守屋等いかりて云はく、「蘇我は勅宣を背きて他国の神を礼す」等云云。又疫病未だ息(や)まず人民すでにたえぬべし。弓削守屋また此れを問奏す云云。勅宣に云はく「蘇我馬子仏法を興行す。宜しく仏法を却(しりぞ)くべし」云云。此に守屋と中臣勝海大連等の両臣は寺に向かって堂塔を切りとうし、仏像をやきやぶり、寺には火をはなち、僧尼の袈裟をはぎ、笞(むち)をもってせ(責)む。又天皇並びに守屋・馬子等疫病す。其の言に云はく「焼くがごとし、きるがごとし」と。又瘡をこる、ほうそう(疱瘡)といふ。馬子嘆いて云はく「尚三宝を仰がん」と。勅宣に云はく「汝独り行なへ、但し余人を断てよ」等云云。馬子ごん(ごんはおのづくりに欠)悦し精舎を造りて三宝を崇めぬ。
天皇は終に八月一五日崩御。この年は太子は十四歳なり。第三十二代用明天皇(治二年欽明の太子聖徳太子の父なり)。治二年丁未四月に天皇疫病あり。皇勅して云はく「三宝に帰せんと欲す」云云。蘇我の大臣詔(みことのり)に従うべしとて遂に法師を引いて内裏に入る。豊国の法師是なり。物部守屋大連等大いに瞋(いか)り、横に睨んで云はく「天皇を厭魅す」と。終に皇隠れさせ給ふ。五月に物部守屋が一族、渋川の家にひきこもり多勢をあつめぬ。太子と馬子と押し寄せてたたかう。五月・六月・七月の間に四箇度合戦す。三度は太子まけ給ふ。第四度めに太子がんを立てて云はく「釈迦如来の御舎利の塔を立て四天王寺を建立せん」と。馬子願って云はく「百済より渡す所の釈迦仏を寺を立てて崇重すべし」云云。弓削なのって(名乗)て云はく「此れは我が放つ矢にはあらず、我が先祖崇重の府都(ふと)の大明神の放ち給ふ矢なり」と。此の矢はるかに飛んで太子の鎧に中(あた)る。太子なのる。此れは我が放つ矢にはあらす、四天王の放ち給ふ矢なりとて、迹見赤ひ(とみのいちひ・ひは木偏に寿)と申す舎人にいさせ給へば、矢ははるかに飛んで守屋が胸に中りぬ。はたのかはかつ(秦河勝)をちあいて頸をとる。此の合戦は用明崩御・崇峻未だ位に即(つ)き給はざる其の中間なり。
第三十三代崇峻天皇位につき給ふ。太子は四天王寺を建立す。此釈迦如来の御舎利なり。馬子は元興寺(がんこうじ)と申す寺を建立して、百済国よりわたりて給ひし教主釈尊を祟重す。』
そこで、平田の死後の世界にまつわる第二点についてもう一度かんがえてみよう。前述のように、平田の記述はというのは、自分の主張に都合のよい事実をうまく拾い集めながら、語りの妙、小出しのやり方で実は、事実とはまったく別の物語を作り上げているのだ、ということがうすうすお分かりになっていただけたと思う。すなわち、小気味よい語りと、わかりやすい切り口上は、実はほとんど平田の都合のよい独りよがり、あるいはほとんど妄想といってもよいレベルになっているということを、良く踏まえておく必要があるのである。
もう一度、平田が死後の世界をかたった文章を引用してみよう。
「すべて親魂(むつたま)あへる徒(とも)どち、またおなじ道ゆく人どちは、死(まか)りて後も、その魂は、一処(ひとところ)に群れ集ひ、互(かたみ)に助(たす)けなすことにて、そは和漢(からやまと)のもろもろの書(ふみ)に記(しる)し伝へたる事実云々」
平田は、仲睦まじかった恋女房が病死してしまったあと、この”霊の真柱”で死後、人はどうなっていくのか、ひたすら思考したようなのである。平田の女房は、病床の床にあって、この著作の完成を弱り切った体で喜んでくれた。上記の文章は、平田が女房に見せた、この”霊の真柱”出てくるのである。この平田の”睦み合える友どち云々”の”睦み合える友どち”という言葉は、平田が恋女房を指して言う時によく使う言葉である。私は平田がこの不思議な世界観をを編み出した裏には、この女房のことが大きく影響しているのではないかと思うのである。死の床についていた女房を看病しながら、必死に平田は考えたに違いないのである。
そこには、死後、ふたた仲睦まじかった女房と再び会える架空の世界を、ひとり空想して作り上げたのではないか。というのが私の考えである。このまさに、ジブリの”火垂るの墓”の蛍の群れを彷彿とさせるがごとき”魂は一処に群れ集い”という言葉は、まことに美しい、現実とは異なるアニメのごとき世界ではないか、と思うのである。そして、その証拠にこの世界は論拠となる文献考察などないことが、最後の”和漢のもろもろの書に記し伝へたる”という怪しげな表現になっているのである。私は、平田のこの死後の世界というのは、先に病死せざるを得なかった女房と平田が死んだのちに睦み合うための、平田がそうあってほしいと願う空想のようなものに違いないと思うのである。すなわち、どう考えても篤胤の空想の世界以外のなにものでもないと思うのである。
私は、平田篤胤という人物は、本当の死の世界というものを直視していない、あるいは直視しようとしない、もっというと、空想と書物の世界に逃げ込んでしまって、ひたすら空想と夢に生きようとする、まことに困った人間だったのではないかと強く思うのである。
”靖国の魂”ともいうべき精神に繋がっていった平田の思想が、単に平田の作り上げた妄想、もっというと、まことに残念ながらただの眉唾ものではなかったのか、と充分疑う余地があるのである。”死しても、魂だけは靖国の桜となって帰ってこれる”、などということを保証をした人間は、実はとんでもない空想家だったのではないか、と私は思うのである。
「平田大角(大角は篤胤の号)なるものは奇男子にござ候。野生も近来往来つかまつり候ところ、その怪妄浮誕(かいもうふたん:とりとめのないでたらめ)にはこまり申し候え共、気概には感服つかまつり候。大角にくらべ候えば松のや(高田与清)などは書肆(しょし)のばんとうぐらいのものにござ候。(中略)三大考を元にいたし附会(こじつけ)の説をまじめにわきまうるはあきれ申し候らえども、神道を天下に明らかにせんと欲し、今もって日夜独学、著述の稿は千巻にこえ候気根、凡人にはござなく候。さりながら奇僻(きへき)の見はもはや堅牢として破るべからず候。うらむべし」
幕末の当時からしてみて、平田篤胤が述べていることは、伝統の神道の見解からは、まったくもって溝をうめることはほとんど不可能な、飛躍をしている。ところが、篤胤があまりに熱心にこの説を繰り返し講演したり、書物に書いたりするため、とうとう一般に広く認知されてしまってまことに困っている、と嘆いているのである。
篤胤に同情的な、同じ国学を志す人でさえこのような感想をもらすのである。ましてや世間一般の人からみる真実の篤胤とは、ただの妄想屋のごときものなのである。